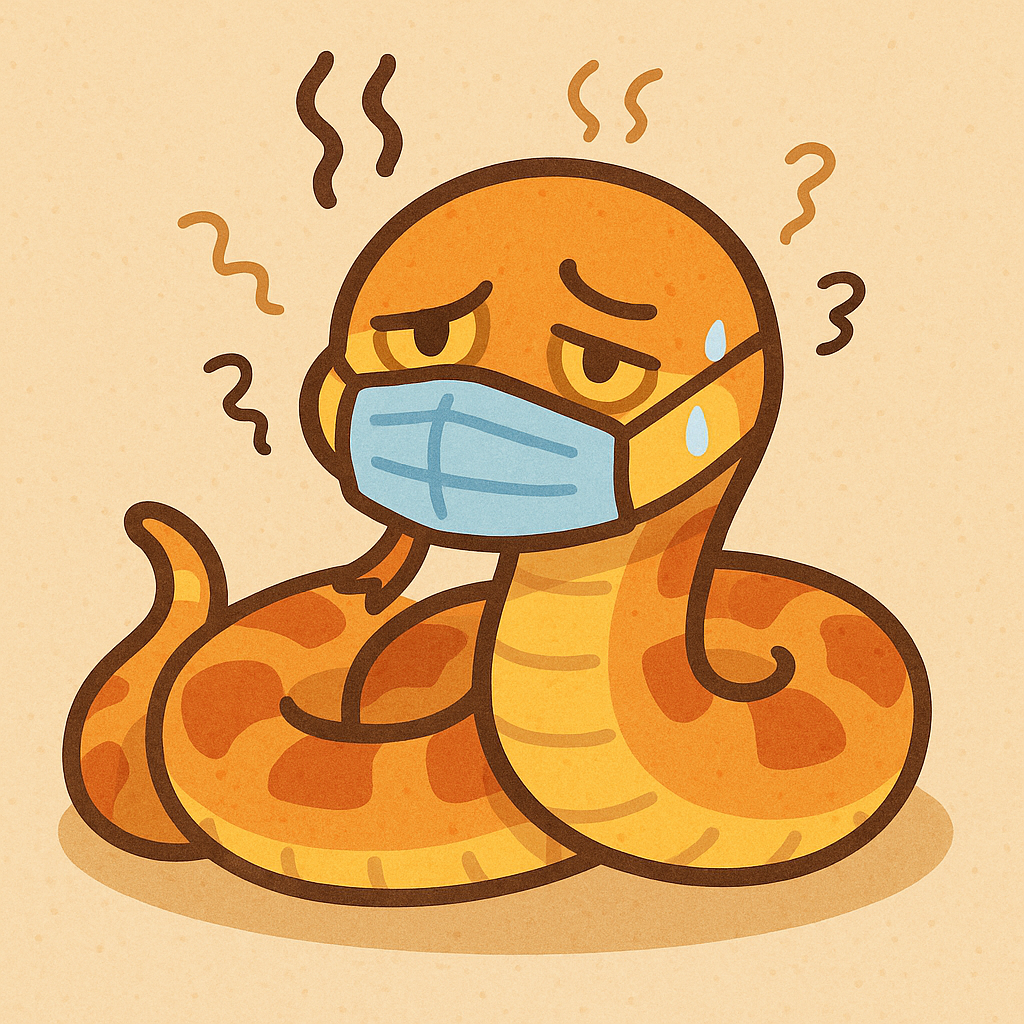ヘビの呼吸器疾患とは?飼育者が知っておくべきこと
ヘビの呼吸器疾患は、カメやヘビでよく見られる病気です。呼吸器の病気は、細菌やウイルス、寄生虫など様々な原因によって引き起こされ、複数の要因が絡み合って発症することも珍しくありません。
ヘビは横隔膜を持たないため、咳をして分泌物を出すことが苦手です。そのため、症状が悪化しやすい傾向にあります。
こんな症状に注意!ヘビの呼吸器疾患のサイン
普段の様子を毎日観察し、少しでも異変を感じたら注意が必要です。特に以下の症状は、呼吸器疾患のサインかもしれません。
・開口呼吸・呼吸困難: 口を開けて呼吸が苦しそうな様子。呼吸の際、体が普段より大きく膨らんでいる。
・呼吸音の異常: 呼吸する際に「シューシュー」といった雑音が聞こえる。
・泡や粘液: 口元や声門(のど)から泡状の分泌物が出る。
・食欲不振: 餌を食べなくなる、活動性が低下する。
・頭を上げる姿勢: 首を伸ばして上を向く、いわゆる「スターゲイジング」と呼ばれる姿勢が見られることがある。
・体色の変化: チアノーゼ(体色の悪化)が見られることがある。
ヘビの呼吸器疾患の主な原因
呼吸器疾患は、感染症と非感染症の2つに大別できますが、多くは複合的な要因で発症します。
感染性要因
1.ウイルス:
・封入体病(IBD): ボア科のヘビに感染し、食欲不振や神経症状、呼吸器症状など多様な症状を示します。ヘビオオサシダニがウイルスを媒介することが知られています。
・ニドウイルス: 飼育下のボールパイソンで、時に致死的な呼吸器疾患を引き起こすことが報告されています。感染力が非常に高く、同居しているヘビに広がることも少なくありません。
2.細菌: 不衛生な環境や免疫力の低下が原因で、グラム陰性好気性細菌(Pseudomonas sp. など)に感染することが一般的です。
3.寄生虫: 舌虫や肺線虫が肺に寄生することで、呼吸器症状を引き起こすことがあります。
非感染性要因
不適切な飼育環境:
・温度, 湿度: ヘビの種に合った最適な温度(Preferred Optimum Temperature Zone: POTZ)と湿度が保たれていないと、免疫力が低下し感染症にかかりやすくなります。
・狭いケージ: 運動不足や不衛生な環境につながり、病気を引き起こす可能性があります。
腫瘍: 肺や気道に腫瘍が形成されることで、呼吸器症状が現れることがあります。
病院での検査と治療の流れ
ヘビの呼吸器疾患が疑われる場合、動物病院では以下のような検査と治療を行います。
診断
・問診・身体検査: 飼育環境や症状を詳しくお伺いし、口の中の状態を確認します。
・画像診断: X線検査や超音波検査、場合によってはCT検査なども含め、肺の状態を詳しく調べます。
・検査: 分泌物を採取し、細菌培養・薬剤感受性試験や細胞診を行うことで、原因菌を特定します。
治療
・環境改善: 適切な温度・湿度に戻し、広めのケージに移します。
・原因治療: 細菌感染の場合は、細菌培養の結果に基づいて適切な抗生物質を投与します。
・支持療法: 輸液や栄養補給を行い、体力を回復させます。
・緊急時の処置: 呼吸が苦しそうな場合は、酸素化を行い、呼吸を楽にさせる処置をすることもあります。
まとめ:早期発見と適切な管理が大切です
ヘビの呼吸器疾患は、飼育環境の不備が原因で発症することが多く、日々の注意深い観察と適切な管理によって予防・改善が可能です。
「ヘビが口を開けたままにしている・口から泡が出ている」「餌を食べない」「呼吸の際に体が大きく膨らむ」など、小さな変化でも見逃さず、できるだけ早く爬虫類を診察できる動物病院にご相談ください。早期の対応が、愛ヘビの命を救うことにつながります。